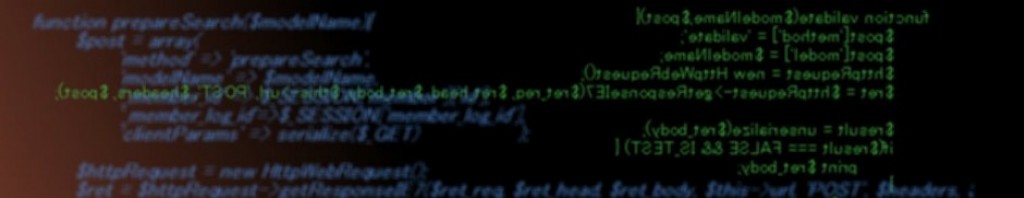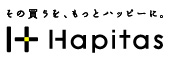クラウドストレージは便利だけど、直接PCで開くのにはやっぱりWindowsファイル共有が便利なんで、お名前.com VPS フレッツ光対応、固定IPサービス「ZOOT NEXT for フレッツ光」
yum install openswan zfs - fuse samba
/ etc / init . d / zfs - fuse start
chkconfig zfs - fuse on
vim / etc / fstab
umount / dev / vdb
zpool create zpool - f / dev / disk / by - path / pci - 0000 \ : 00 \ : 05.0 - virtio - pci - virtio2
zfs create zpool / public
zfs dedup = verify zpool / public
パッケージ導入、ZFS-fuse起動設定、fstabの/dataのマウント設定を削除、デフォルトの/dataを削除してzpoolを作成し、zpool/publicを重複除外有効にした。 ZFS-fuseではfstabマウントでは無く、ZFS-fuse側の設定でマウントする。
次にIPSecの設定を行う。 設定ファイルの編集 /etc/ipsec.conf
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
version 2.0
config setup
protostack = netkey
nat_traversal = yes
virtual_private = % v4 : 192.168.0.0 / 16
oe = off
conn home
type = tunnel
authby = secret
auth = esp
keyexchange = ike
ike = 3des - sha ; modp1024
phase2 = esp
phase2alg = 3des - sha ; modp1024
pfs = no
left = お名前固定IP
leftid = お名前固定IP
leftsubnet = お名前固定IP / 32
right = IX2025 外IP
rightid = IX2025 中IP
rightsubnet = 192.168.0.0 / 23
auto = start
自宅のローカルは192.168.0.0/23でIX2025は192.168.0.1になっている。
お名前固定IP 192.168.0.1 : PSK "共通シークレット"
あとは、カーネルパラメータを修正する必要があるので、/etc/sysctl.confを編集(上側の修正はipsec verifyコマンドの指示に従っている。 IP_ForwardはOnじゃないとトンネリング出来ない)
net . ipv4 . conf . all . send_redirects = 0
net . ipv4 . conf . all . accept_redirects = 0
net . ipv4 . conf . default . send_redirects = 0
net . ipv4 . conf . default . accept_redirects = 0
net . ipv4 . conf . eth0 . send_redirects = 0
net . ipv4 . conf . eth0 . accept_redirects = 0
net . ipv4 . conf . lo . send_redirects = 0
net . ipv4 . conf . lo . accept_redirects = 0
#net.ipv4.ip_forward = 1
編集後に適用
あとは、iptablesに穴開けするため、/etc/sysconfig/iptablesを編集。
- A INPUT - s 192.168.0.0 / 23 - j ACCEPT
- A INPUT - p udp - s IX2025 外IP / 32 -- dport 500 - j ACCEPT
- A INPUT - p udp - s IX2025 外IP / 32 -- dport 4500 - j ACCEPT
- A INPUT - p esp - s IX2025 外IP / 32 - j ACCEPT
IPSecに関係するUDP500とそのNAT Traversalである4500、そしてESPを許可する。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ip route お名前固定IP / 32 Tunnel1 . 0
ip access - list onamae - acl permit ip src any dest any
ike nat - traversal
ike suppress - dangling
ike proposal onamae - ike - prop encryption 3des hash sha group 1024 - bit
ike policy onamae - ike peer お名前固定IP key 共通シークレット onamae - ike - prop
ike keepalive onamae - ike 30 3
ike local - id onamae - ike address 192.168.0.1
ike remote - id onamae - ike address お名前固定IP
ipsec autokey - proposal onamae - ipsec - prop esp - 3des esp - sha
ipsec autokey - map onamae - ipsec onamae - acl peer お名前固定IP onamae - ipsec - prop
! pppoe インタフェース上のudp 500 , 4500 , ESP ( Protocol : 50 ) のNAPT 設定等は別途設定済み
interface Tunnel1 . 0
tunnel mode ipsec
ip unnumbered GigaEthernet0 . 1
ip tcp adjust - mss auto
ipsec poict tunnel onamae - ipsec out
no shutdown
プロポーザル関係の設定が中心。
/ etc / init . d / ipsec start
chkconfig ipsec on
数秒でネゴシエーションされて、IX2025のshow ike saでph1/ph2を確認する。
(389)
を購入したんでPlayストアを入れた話。